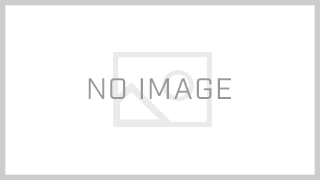最近では多くの女性にも爆発的な人気のDIY。
雑誌などを見ると雑貨や棚などの小物制作、壁や床などの簡易的なリフォームなどをイメージしている人が多いようですが、あなたは「DIY」についてどの程度知っているでしょうか?
この記事ではDIYって何?から、日曜大工やハンドメイドとの違いをからDIYを楽しむための7つのステップと、初心者がやりがちな10の失敗例とその対処法を解説していきます。
これからDIYを始めたい!をいう方は最初に読んでいただくと参考になると思いますし、すでにDIYを始めている方は復習だと思って見てもらえれば嬉しいです
DIYとは何の略?
そもそも「DIY」の語源は「Do It Yourself」からきています。
この3つの単語の頭文字をとって「DIY」と呼ばれています。日本語に訳すと「自分でやってみよう!」という意味になります。
この「自分にできることは自分でやってみよう!」という考え方がDIYの基本理念であり、そして棚や収納、テーブルに椅子などを自分で作ったり修理したりして、自分の好きな物を作る楽しさがDIYにはあります。
最近では100均で様々なDIYに使えるグッズが販売されるようになり、誰でも簡単に始められるようになったのも、女性に爆発的に人気になった要因ではないでしょうか。
100均で購入したものを組み合わせるだけで自分だけのオリジナル小物ができるので、それらを部屋に置けば簡単にイメージを変えられます。
インテリアを統一させたり、便利グッズを自分で制作し有効利用するためにもDIYはおすすめです。
DIYの歴史
DIYという言葉が生まれたのは1945年まで遡ります。
第二次世界大戦でドイツ軍から激しい攻撃を受けたイギリスのロンドンにおいて、戦後に破壊された自分たちの街を自分たちの手で復興させよう!という国民運動が始まりました。
その時に掲げられたスローガンこそ
「Do It Yourself」 自分にできることは自分でやってみよう!だったのです。
この運動がイギリス中を席巻し、やがてヨーロッパ全土に広がり、そしてアメリカ合衆国へと広まりました。アメリカに伝わった時から「DIY」は復興から「楽しむ」という概念に変化し、いつの間にか週末にパパがやる趣味へと変わっていきました。
そのころからホームセンターなどで専門の工具や材料が各地で販売されるようになる、多くの愛好者が生まれ始めました。
日本には1970年頃に上陸されたと考えられてます。
日本では「日曜大工」として浸透していましたが、ホームセンターなどの戦略で「DIY」と言う言葉が一般的に浸透し、現在、100円均一ショップなどの普及により更に人気が出ています。
このように元々DIYは復興という考えでした。現代では復興という考えはありませんが、リメイクしたり修理するという考えは本来の意味に近い考えかもしれませんね。
日曜大工とは同じなの?
日本ではDIYという言葉より「日曜大工」の方がしっくりくる人が多いかもしれませんが、厳密にいうとDIYと日曜大工は違います。
厳密にいうとなのでほとんど一緒なのですが、日曜大工とは言葉の通り、お休みの日に大工仕事をすることです。この大工仕事とは木工作業の事を指しています。
対照的にDIYとは主に棚や収納などの小物を制作することも含まれています。このような小物制作を日曜大工とは言いません。
つまり、趣味で木工作業のみをすることを「日曜大工」と言い、木工作業を含めた手作り作業をすることを「DIY」と言います。
DIY愛好家の方で木工専門という方は日曜大工であり、日曜大工で小物などの制作をすれば、それはDIYとなってしまいます。
とても分かりづらいですが、DIYをやっていると言えば何も問題ありません。
ハンドメイドとの違いは?
ではハンドメイドとDIYは何が違うのか?こちらも厳密に言えば違いがあります。
ハンドメイドとは「手作り」という意味です。したがって手作りであれば全てがハンドメイドとなります。
ではDIYと一緒ではないかと思うのですが、違いが2つあります。それは、プロの作家さんが作ったもの、例えば手作り絵本や手作りぬいぐるみ、そして手作り積み木などが挙げられます。
1つ目の違いは木工作品ではなくてもハンドメイドではあるという事。
2つ目は木工作品を販売していること。
この2つがDIYとは違う点です。あくまでもDIYは趣味で木工作業をすることです。もしそれらの作品を販売するとなると、その作品はDIY作品ではなく、ハンドメイド作品となります。
厳密にいうとDIYでも木材以外を使用することはありますが、あくまでも定義の問題として解釈してください。
自分でやってみよう!
DIYとは街の復興精神から始まり、現在では多くの愛好家が物づくりを楽しんでいます。
DIYの原点である「自分にできることは自分でやってみよう!」の精神はとても素敵な考え方ではないでしょうか?
何でも電話1本で解決できてしまう時代。また、気に入らないことがあればすぐにクレームをする人や、SNSで他人の中傷をする人達が多くなっている現代において、自分にできることは自分でやってみる事は心を豊かにする薬となるかもしれません。
自分で作った小物が部屋に置いてあるだけで心が豊かになる。それがDIYの最大の魅力だと私は思っています。
DIYの基本
長年、大工としてモノづくりをしてきましたが、DIY(木工)とは
「測って、切って、留める」の繰り返しだと思っています。
小さな棚でも住宅1軒でも一緒です。サイズを決めて材料をその通りにカットして留める。住宅を建てる時もこの作業の繰り返しです。
基本はこの3工程で、あとはそれぞれの精度を上げていくだけです。
そして最後に「仕上げる」という工程があって作品は完成します。
住宅の場合だと、大工さんが下地を「測って、切って、留めて」作った後に、内装屋さんが壁紙(クロス)で仕上げます。DIYだとヤスリで削ったり塗装をしたりする工程のことです。
どんなに複雑な物でも基本は一緒。だからまずは基本をしっかりと身につけましょう!
では、DIYの基本工程を7ステップに分けて解説していきますね。
ステップ1 寸法を決める
まず始めの工程は作る物の寸法を決める事です。
設置する場所の寸法を測り、作成する作品の、幅・高さ・長さを決めましょう。
例えば棚の中に入れる箱を作りたい時は、棚の幅と奥行きを計測して、完成させる作品のイメージを考えましょう!

ステップ2 図面を書く
次は簡単でいいので図面を作ってみましょう。
フリーハンドの手書き図面でも構いません。図面を書くことの理由は2つあります。
1つは自分の考えがまとまること。2つ目が材料購入の際に参考になることです。どちも重要なことなので簡単でもいいので図面を作ってみましょう!
図面を書くのが苦手な方は無料のソフトがありますので、使ってみてはいかがでしょう。私がおすすめする図面作成ソフトは「もでりん」です。パソコンがあれば誰でも簡単に図面が作れてしまいます。
【もでりん画面サンプル】

ステップ3 材料を準備する
作る作品が決まったら材料を仕入れしましょう。
ホームセンターで仕入れするのが一番簡単でしょう。大きくても6フィート(1820m)くらいの材料で済むようにすれば車や手で何とか運べるサイスです。
どうしても大きな材料がいる場合はホームセンターでトラックを貸してくれるサービスがありますので、そちらを活用しましょう!
事前に図面を作っておくと仕入れの際に非常に便利です。
ステップ4 測って切る
材料を購入してきたら、図面通りに測って切断しましょう。
ほとんどの場合は直角に切断すると思うので、「さしがね」を使ってしっかりと90°を出してから切断しましょう。90°は必ず2方向に印をつけてから切断しないと直角に仕上がりませんので注意が必要です。

ステップ5 留める
材料の切断が終わればいよいよ、ビスや釘などで留めて組み立てます。
基本的にはビスで留めることをおすすめします。初心者の頃は材料を固定しないと上手くビス留めができないため、クランプで材料を固定してからビスで留めるようにしてください。

ステップ6 仕上げ
最後は紙やすりで仕上げていきましょう。
塗装は好みに応じて使い分けます。オイルステインなどの簡単に塗装ができる製品がホームセンターで売られているので、使ってみて自分らしい作品を作ってみてください。
よくある失敗と7つのコツ
以上の6ステップがDIYの超基本手順でした。
次は初心者がよくやってしまう失敗例とそうならないためのコツを10個解説していきます。
どれも些細なことなんですが、初心者が必ずといていいほどやってしまう失敗ですので是非参考にしてください。
ぴったりで作らない
初心者でも上級者でもやってしまう失敗。寸法カッチリに作ってしまう失敗です。
上級者になればなるほどピッタリと作りたくなるのですが、作品のサイズはゆったりと作成することをおすすめします。
作ってから気が付く事って本当に多いんです!「大は小を兼ねる」と言いますがDIYでは「小は大を兼ねる」だと思います(笑)
大きい物は何をやっても入らない!どうしても入れたいものや、のせたい物がない限り作品のサイズは小さめに作ることをおすすめします。
スケールの長さ
こちらもピッタリで作らないの延長なのですが、スケール(メジャー)の使い方を間違えると寸法がきつくなって失敗します。
スケールの先端の引っ掛ける所がありますよね。ここって「遊び」があってぐらぐらします。感覚的に2~3mm動きます。
つまり伸びた時と縮んだと気で3mmくらい長さが違うってことです。細かいようですがギリギリで作成するとこの3mmが致命的になります。
例えば寸法を図る時にこうやって測って

材料を図る時にこうやって測ると

3mm近く長さが変わってきます。細かいですが棚板を作る場合だったら、切断した板が入らなくなります。
そうなったら大変。板を3mmだけ切るのは物凄く大変なんです。プロでも難しい。
卓上のこぎりか、かんなでないと対応できませんので、材料は余裕をもって測りましょう!
材料の厚みを考慮する
こちらもよくある失敗例で、材料の厚さ分を考慮し忘れることです。
例えば下記のような棚を作る時に、両サイドの板(赤斜線)と真ん中の板(赤)では長さが違いますよね?

両サイドの板の長さから上下のいた分の厚さを引かないと真ん中の板の長さは分かりません。非常に単純なミスなんですがDIYあるあるってほどよくやる失敗です。
例のように単純な作品であれば間違わないかもしれませんが、複雑になると間違える可能性は高まります。
対処法としては、やっぱり設計図を作ることです。頭の中で考えて見切り発車で始めると失敗します。
参照画像は私がおすすめの「もでりん」です。ボタン一つで採寸長さもわかるのでとっても便利です。

どんな寸法の材料があるか知っておく
ホームセンターにどんな寸法の材料があるか知っておくことも重要です。
自宅で設計図を書いたのに、いざホームセンターに行ってみたら思うような寸法の材料が無かった・・・・
そうすると全ての計画が台無しになってしまい、材料購入ができなくなってしまいます。
ですので、事前にホームセンターに置いてある材料をメモっておくことも重要です。自分のメインとなるホームセンターを1つ選んでおくことをすすめます。
2×4材が一番のおすすめです。全国どこのホームセンターでも販売していますし、規格化されていてラインナップも多いからです。
その他に自分に合った材料を数点メモっておけば失敗することはありません。
ホームセンターでカットするのもアリ
材料のカットが上手くいかなくてDIYを挫折する人は多いです。特に大きな材料を手動でカットすると疲れます。
なのでホームセンターでカットしてもらう選択もアリです。1カット30円程度で切断してくれますので、そちらを使ってみてはいかがでしょうか。
ホームセンターでカットをお願いする場合は事前に設計図を作っておくとよいでしょう!
どうしてものこぎりでカットしたい人はのこぎり専用の「ソーガイド」などを使って下さい。
やわらかい素材を選ぶ
初心者がは材質が分からないため、固めの材料を選んでしまうことがあります。
初心者はやわらかく施工しやすい材料を選ぶべきです。
特に「桐」は紙か?ってくらいやわらかい材料なので容易に加工ができます。が商品ラインナップが少ないため、「杉」がおすすめです。
桐に比べてラインナップは多いですが、SPF材に比べれば少ないので、DIYに慣れてきたらツー材のSPFを使うのが良いでしょう。
SPF材は杉に比べて少し硬めですが、種類も豊富なのでこの材質になれることが重要です。
初心者が買ってはいけない材質は「松」です。特に米松(べいまつ)と表記のあるものは非常に硬く、加工が難しい材料です。
床や屋根などがある構造材以外ではおすすめできない材料なので気を付けてください。
ビスで材料にヒビ
初心者が最もやってしまう失敗、それは材料にヒビを入れてしまうことです。
慣れてくるとどうすればヒビが入るか大体わかってくるのですが始めは失敗することがよくあります。
材料の先端でビスを締めるとヒビが入る可能性が高いです。図のように木目方向の端(A)にビスを打ち付けるとヒビが入ります。同じ端でも(B)はヒビが入りません。

木目の関係なので(A)のような場所にビスを締めたい場合は少し離して締めてください。

↑これだとヒビが入るので

↑これくらいの位置で締めてください。
どうしても端で締めたい場合は、ビスを締める前にドリルで下穴を開けておきましょう!
ビスと釘の長さ
どんな長さのビスや釘で留めればよいか?もよくある疑問です。
状況にもよりますが基本的に
釘の場合は留める材料の厚みの2.5倍。
ビスに場合は留める材料の厚みの1.5倍。
これらを基準にしておくと良いでしょう!例えば厚さ19mmの1×4材を留める時は
釘の場合は48mm以上、ビスの場合は29mm以上を使うとよいでしょう。
あくまでも参考ですが、必要以上に長い釘やビスを使うと曲がったりビスの頭が潰れる原因となりますので、適切な物をつかうと失敗は少なくなるでしょう。
紙やすりで仕上げる
作品が完成したら紙やすりで仕上げに入ります。
ここでよくある質問が何番の紙やすりを使えばいいか?という疑問です。
紙やすりは番手が多くなればなるほど細かくなっていきます。私の場合は用途に分けて使う紙やすりが違います。
作品の角を滑らかにする(面取り)ためにまずは100番程度の紙やすりで面取りをします。
その後に180番程度紙やすりで全体的を仕上げます。綺麗に仕上げようとすればさらに細かい番手の紙やすりを使って仕上げますが、一般的には必要ありません。
仕上げをするときのコツは画像のように木材に巻き付けて使うと上手く仕上げることができます。

自宅で塗装は慎重に
塗装仕上げをするかしないかは自由ですが、自宅で塗装仕上げをする場合は慎重に。
当たり前ですが床や壁に付いたら大変です!しっかりと養生をして取り組んでください。最低限、床は小さなブルーシートなどで養生してください。
そして使用する塗料のニオイにも注意が必要です。なるべくニオイの少ない塗料を選んで仕上げてください。特に油性などの塗料は強烈なニオイがする商品もありますので注意が必要です。
DIYは一般的にオイルステインをウェスでふき取るように仕上げますが、中でもニオイの少ない「ワトコオイル」がおすすめです。
私は個人的に好きなニオイです。
最後に
以上がDIYの基本と失敗例です。
まだまだコツや知識は沢山ありますが、まずはこの基本知識を覚えてDIYを始めてください。
始めようか悩んでいる人がいたら是非すぐに始めてください!沢山の知識を習う前に始めてください。まずはDIYの楽しさから実感してください。
好きになったら次の知識を覚えていけばいいんです。とりあえず簡単な棚なんかを作ってみて、「楽しい!」って思うことが最初の1歩です。